46枚貸しは得なのか損なのか?導入の理由とメリットを解説!
近年、スロットの貸し出し枚数として「46枚貸し」「47枚貸し」を掲げるホールが急増しています。
以前主流だった「50枚貸し」から変化したこの仕組みは、単なる気まぐれではありません。
業界全体の流れや消費税の影響、そしてホール経営上の戦略が背景にあります。
しかし、打ち手にとっては、
・損なのか?
・得なのか?
・なぜ変わったのか?
が分かりづらく、誤解されやすい部分でもあります。
この記事では、46枚貸しの導入理由や仕組みをわかりやすく解説しながら、実際にどれほどのメリット・デメリットがあるのかを数字を交えて検証します。
知らないうちに損をしている人も多いため、この記事を読むことで46枚貸しの本当の意味と、立ち回りで意識すべきポイントを理解できるはずです。
46枚貸しはなぜ導入されたのか?
スロットの貸出方式として「46枚貸し」や「47枚貸し」が広く見られるようになった背景には、税制や業界構造の変化が関係しています。
もともとスロットは、1,000円で50枚を借りられる「50枚貸し」が一般的でした。
しかし消費税が5%から8%、そして10%へと段階的に引き上げられる中で、ホール側が消費税を内部で吸収するのが難しくなります。
そこで、法律上認められた範囲内で、「1枚あたりの単価を上げる」という形をとったのです。
実質的にお客さん側に、消費税分を負担させる方法が採用されました。
この時、小銭のやり取りをサンド(貸出機)で行うことができません。
そのため、端数分を調整する手段として、枚数を減らす方式が選ばれました。
50枚貸しから47枚貸し、さらに46枚貸しへと変化していったのは、まさにこの計算上の調整結果です。
消費税10%の現行制度では、1,000円あたり21.73円が上限となります。
結果として、46枚貸しが最も実務的で整合性のある形として普及しました。
つまり46枚貸しは税制対応であり、ホールの利益を確保するための現実的な選択肢と言えます。
また、貸出単価を上げることで、店舗側の売上も増加しやすくなります。
等価交換を維持しながら税負担を抑え、運営コストを補う仕組みとして多くのホールが採用するようになりました。
特に神奈川や埼玉などの一部地域では、46枚貸しのまま等価交換を認める条例運用がなされており、46枚等価の店舗も存在します。
これにより、打ち手の感覚的な違和感を少なくしつつ、ホールの経営効率を上げることに成功しているのです。
消費税対応が主な理由だった
46枚貸しの最大の理由は、税率引き上げに伴う「外税化」です。
もともとホールは、貸し出し時のメダルに対する消費税を内部で負担していました。
しかし、税率が8%になった2014年頃から、店舗側がそれを価格に反映させることが許可され、メダルの単価を上げる方式に移行します。
8%のときは47枚貸し、10%になってからは46枚貸しが主流となりました。
46枚という数字は、
1000÷22=45.45
という計算から導かれた上限値を、四捨五入したものです。
このため、46枚貸しは法律上の上限値に近い、最も現実的な設定といえます。
単に「枚数を減らした」わけではなく、消費税を考慮したうえでの合理的な調整結果なのです。
この仕組みを理解すれば、「なぜ46枚貸しなのか?」という疑問は自然に解消されます。
税率変動による制度的な対応であり、ホール側が一方的に不当な利益を得るための仕組みではないことがわかります。
複合的な要因が絡み合った結果
従来の50枚貸し時代は、1,000円で50枚を借りられ、50枚で1,000円に交換できる等価が多く存在しました。
しかし、税制改正後は46枚貸し・47枚貸しへと移行し、1枚あたりの単価が上昇。
たとえば1,000円で46枚の場合、1枚は約21.7円に相当します。
このため、等価であっても単価が上がる分、投資額の総額が増える仕組みになります。
その一方で、非等価交換を採用しているホールでは、46枚貸しで51.2枚交換などの形を取っています。
これにより、見かけ上のバランスを取っているケースもあります。
こうした設定により、ホール側は消費税分を補いつつ、一定の還元する余力を残しているわけです。
ただし、実際に現金投資を続けると、貸し枚数が少ないほど1,000円あたりのプレイ回数が減ります。
長時間遊ぶほど、損失が膨らむ傾向に…。
46枚貸しの登場は単なる数字変更ではなく、業界の税制対応・経営合理化・お客への還元率の再調整という、複合的な要因が絡み合った結果なのです。
46枚貸しスロットを打つメリット
46枚貸しの最大のメリットは、出玉を換金した際の金額が、従来よりもわずかに高くなる点にあります。
単価が上がっているため、同じ枚数のメダルを交換したとしても、換金額が高くなるのです。
例えば、1,000枚のメダルを流した場合、50枚貸しでは17,800円程度ですが、46枚貸しでは約19,300円になります。
この差額はおよそ1,500円。
少額のように見えますが、長期間打ち続ければ大きな違いとなります。
また、46枚貸しではホール側の総貸出金額が増えるため、還元の余地を持たせることが可能です。
設定配分に余裕をもたせやすくなり、結果的に高設定台が投入されやすい傾向にある店舗も存在します。
この構造により、理論上は「遊べる環境」を維持しつつも、打ち手が勝てるチャンスを残すという両立が図られています。
さらに、税制対応を終えた上での経営安定化が図れるため、閉店リスクも軽減。
これは長期的には、打ち手にとっても安心材料になります。
従来よりギャンブル性が高くなった
46枚貸しでは、1枚あたりの貸出単価が上がる分、換金時の金額も上がります。
例えば、1,000円で借りられるメダルが50枚から46枚に減ったとしても、等価交換であれば、メダル1枚の価値が従来よりも上昇しています。
つまり、同じ枚数を出しても換金額が高くなるため、理論上は勝った時の金額が増える仕組みです。
今までより、ギャンブル性が高くなった、大勝ちできるようになった、と言えます。
この違いを具体的に比較すると、5,000枚を流した場合の換金額は以下のようになります。
・50枚貸し=約89,000円
・47枚貸し=約95,000円
・46枚貸し=約96,900円
単純計算で、およそ7,900円もの差が出ます。
スマスロで一撃出した際や、また長期目線で見れば、この差は無視できない存在でしょう。
出玉が大きいほど、利益の伸び幅も拡大します。
そのため、同じ勝率でも一度の勝ちで得られる金額が増え、長期的には総合収支を底上げする効果があります。
等価交換ならハイエナも有利
46枚貸しの等価交換は、特にハイエナのように期待値を重視する立ち回りにおいて有利です。
非等価交換では現金投資による損失が出やすく、貯メダル再プレイが制限される場合もあります。
しかし46枚等価交換では、現金投資と回収が完全に等価であるため、台移動や再プレイ時の損失が発生しません。
また、等価であることから、1枚あたりの期待値も上昇。
非等価と比較して、最大1.08倍の効率で期待値を積み重ねることが可能です。
さらに、等価交換地域では貯メダルの制限も緩く、再プレイ上限がない店舗も多いため、立ち回りの自由度が格段に上がります。
抽選で狙い台が取れなかった場合でも、ハイエナ稼働への切り替えが容易で、結果的に収支を安定させることができます。
このように46枚等価交換は、短時間勝負にも向いています。
効率的な稼働を目指す打ち手にとって、強い味方です。
ホールと客の双方に利点がある
46枚貸しは、ホール側の利益確保策であると同時に、お客さん側にも一定の利点があります。
ホールは、貸出単価が上がることで消費税分を確実に回収でき、経営安定性を高めることができます。
一方で打ち手側は、等価または準等価交換を前提とすることで、出玉を換金した際の戻り金が増えるという形で恩恵を受けます。
この構造により、店舗が倒産や閉店に追い込まれるリスクを減らし、打ち手が長期的に遊べる環境を維持できるという、WIN-WINな関係が成立します。
ホールの体力が維持されることで、イベント開催や高設定投入といった還元施策にもつながります。
結果的に46枚貸しは、相互利益を生む構造と言えるでしょう。
46枚貸しにもデメリットはある
46枚貸しには一見すると、気付きにくいデメリットが多く存在します。
貸出単価が上がることによって、1,000円あたりに遊べる回転数が減少。
結果的に打ち手は、短時間でより多くの資金を失いやすくなります。
たとえば、50枚貸しで1,000円なら50枚のメダルを借りられますが、46枚貸しでは同じ金額で46枚しか手に入りません。
そのため、同じ台を同じ時間打っても投資スピードが速まり、負けたときの金額が大きくなりやすいのです。
また、ホールはこの高レートを利用して、利益を得やすくなります。
仮に設定配分が50枚貸し時代と同じであっても、1枚あたりの価値が高いため、客側の負担は確実に増えます。
つまり、勝ったときの金額はやや増えますが、負けたときのリスクはそれ以上に高くなる構造です。
この点が、46枚貸しが「損をしやすい」と言われる最大の理由です。
投資額が増えて利益が出にくい
46枚貸しでは1,000円あたりの貸出枚数が少ないため、同じ展開でも投資総額が増えやすくなります。
たとえば、1,000枚のメダルを使って初当たりを引いた場合、50枚貸しではおよそ20,000円の投資です。
しかし46枚貸しでは、21,750円を消費している計算になります。
さらに、これを6.0枚交換で換金したとすると、回収は18,115円にとどまり、結果として赤字になります。
このように、単純な数字の違いであっても、投資と回収のバランスが大きく変化します。
枚数が減った分、1枚あたりの重みが増し、少しの負けでも金額換算では痛手が大きくなるのです。
高設定台を掴んだとしても、この不利なレートを完全に打ち消すのは容易ではありません。
打ち手側の実質的な勝率は、46枚貸しの普及によって明確に下がっていると言えます。
非等価交換ではさらに不利になる
近年では、多くの地域で等価交換が禁止され、5.6枚や6.0枚交換が標準化されています。
この非等価環境で46枚貸しが組み合わさると、損失はさらに拡大します。
同じメダル数を換金しても戻ってくる金額が減り、実質的な機械割が低下してしまうのです。
たとえば、50枚貸しの6.0枚交換では1万円投資して8,330円の戻りです。
しかし、46枚貸しの6.0枚交換では、さらに差が広がります。
10万円を投資した場合、
・50枚貸しでは5,000枚
・46枚貸しでは4,600枚
しか得られず、400枚=約8,000円の差が生じます。
この差は長期的に見れば、無視できない損失です。
加えて、換金ギャップの影響により、実際の機械割は設定値よりも低くなります。
6号機の設定6の理論値114.9%が、実質では100%を下回る場合すらあります。
現金投資を続けるほど損が増える
46枚貸しの非等価では、現金投資を続けるほど不利になります。
貯メダルを活用せずに毎回現金で打つと、その都度交換ギャップ分の損が発生します。
1万円あたりおよそ1,000円の損失が出る計算であり、これを繰り返すと月単位で大きな差となります。
たとえば、46枚貸し50枚交換の店舗では、現金で1万円を入れて460枚を借り、同じだけ回収しても10,000円に戻らず、端数分も確実に損失になります。
そのため、頻繁に現金を使うお客ほど負担が増え、結果的に勝ちづらい環境となります。
この構造を理解せずに打ち続けると、知らぬ間に損を積み重ねていることになるのです。
46枚貸しは本当に損なのか?数字で検証
46枚貸しは「損」と言われがちですが、正確には状況によって評価が分かれます。
たしかに、現金投資を多く行う人にとっては不利な仕組みです。
しかし、等価交換や貯メダルを活用している場合は、それほど大きな損失にはなりません。
ここでは、具体的な数字を用いて、46枚貸しが実際にどれほどの影響を与えるのかを確認していきます。
数千枚単位では確実に影響がある
46枚貸しでは、1枚あたりの単価が上がるため、同じ枚数を出しても換金額に差が生まれます。
例えば、1000枚の出玉を換金した場合、50枚貸しでは17,800円前後ですが、46枚貸しでは約19,300円になります。
この差は1500円程度であり、勝った時は確かに得をしたように感じます。
しかし、実際にはその分、投資段階で多くの金額を支払っているため、トータルで見れば大きなメリットにはなりにくいのです。
また、50枚貸しの20.00円と比較した場合、1枚あたりの金額は、
・47枚貸しで21.28円
・46枚貸しで21.74円
となります。
この違いはわずかに感じるかもしれませんが、数千枚単位での遊技では確実に影響を及ぼします。
貸し枚数が少ないほど1回転ごとのコストが上がり、実質的な投資効率が下がってしまうのです。
非等価では不利さがさらに顕著に
非等価交換の地域では、46枚貸しの不利さがさらに顕著になります。
例えば、46枚貸し50枚交換の場合、1000円を入れて460枚借りたとしても、換金する際には500枚で1000円相当しか戻ってきません。
つまり、同じだけのプレイをしても、毎回確実に損を積み上げていく構造です。
1万円を現金で投入した場合、約1,000円前後の欠損が発生するとされており、10万円使えば単純計算で1万円のロスとなります。
現金投資を繰り返すほど不利になり、貯メダルを使わない人は、確実に損失を拡大させることになります。
このような環境では、打てば打つほど損を積み重ねる結果となり、長期的に見ると勝率の低下が避けられません。
貯メダルを使えば損を軽減できる
46枚貸しで損をしないための対策として、最も有効なのが貯メダルの活用です。
現金投資を避けて、貯メダルで再プレイすれば、貸出時の外税分を支払う必要がなくなります。
そのため、現金を使うたびに発生していた、1,000円あたりの損失を防ぐことができます。
たとえば、1万円で460枚を借り、500枚を回収した場合、現金遊技ではほぼトントンに見えても実際には損をしています。
一方、貯メダルを利用すれば、そのままメダルを再利用できるため、毎回の交換差によるロスが発生しません。
特に頻繁に通う店舗では、この差が月単位で数千円から数万円にもなるため、貯メダルの有無が大きな分かれ道になります。
貯メダル(貯玉)については、こちらの記事で詳しく説明しています↓
貯メダルにも、メリット・デメリットがありますので、まずは理解することが大切ですね。
パチンコは貯玉で打つと当たらない?再プレイは現金より勝てないのか解説!
パチンコでタバコに交換は得?景品と現金や貯玉のどれがいいか解説!
打ち手によって得か損かが変わる
46枚貸しの影響は、遊技スタイルによって大きく異なります。
短時間勝負や設定狙いをする層にとっては、勝てば利益額が増えるためプラスに働くこともあります。
しかし、長時間打つ人にとっては、投資がかさむほど不利に作用します。
特に、確実に勝てる台を狙える人、ハイエナのように機械割を意識して立ち回る人には、レートが高いほど効率的に収支を上げられる可能性があります。
一方で、設定状況が読めないホールで漫然と打つ人にとっては、46枚貸しはリスクを拡大させる要因となります。
要するに、打ち手の力量によって「得か損か」が変わるのが、この制度の本質です。
46枚貸しの今後と業界の動き予想
46枚貸しは一時的な制度ではなく、業界全体が採用した合理的な仕組みとして定着しています。
消費税10%の現行制度下では、1,000円あたり21.73円が上限値です。
そのため、46枚貸しが法的にも実務的にも、最適なライン。
したがって、今後も税率の変更がない限り、この貸出枚数が基本として維持される見通しです。
また、非等価交換が主流になった現在では、ホール間の差別化が難しくなっています。
店舗ごとに46枚貸しを基準にしつつ、交換率や再プレイ条件で、独自のサービスを打ち出す傾向が見られます。
打ち手側も、46枚貸しが当たり前の時代として受け入れつつあり、以前の50枚貸しを知る層からも「仕方ない」との声が多くなっています。
そのため、今後の焦点は46枚貸しを前提に、
・どう遊ぶか?
・どうすれば損を減らせるか?
という点に移っています。
業界全体での標準化が進む
2019年の増税以降、47枚貸しや46枚貸しを導入するホールが、全国的に拡大しました。
この流れはもはや一過性ではなく、ほぼ全ての主要チェーンが導入を完了しています。
特に神奈川や埼玉など、一部地域では46枚等価交換の店舗が多く、業界大手もこの方式を採用しています。
このことからも、46枚貸しは単なる税対策を超えて、業界標準のレートとして定着したことが分かります。
一方で、地域によっては条例や組合規制により、非等価交換しか認められない場合もあります。
そのため、同じ46枚貸しでも、交換率や再プレイ条件に違いがあり、実際の還元率は店舗ごとに異なります。
結果として、数字上は同じ46枚貸しでも、実際に得られる利益や損失は、ホール次第で変わることになります。
税制改正や景品基準の影響も
46枚貸しの存在は、消費税率と密接に関係しています。
もし、今後税率が変更された場合、再び47枚貸しや45枚貸しなどに、調整される可能性があります。
これは過去にも起きた変化であり、消費税8%時代には47枚貸しが主流でした。
また、特殊景品への交換時に「貸玉・貸メダルの112%」を上限とする「一物一価のルール」も影響しています。
貸出価格に対して、一定以上の還元ができないように統一されているため、ホールは税率変動に合わせて、貸枚数を微調整しなければなりません。
このため、46枚貸しは税制が変わらない限り続くものの、制度的には柔軟に変動する仕組みといえます。
総合的に見て判断することが重要
46枚貸しが標準となった現在、打ち手が意識すべきは「店舗ごとの差」です。
同じ46枚貸しでも、交換率が異なれば収支結果はまったく違います。
例えば、46枚貸し46枚交換なら等価です。
しかし、46枚貸し50枚交換の非等価環境では、現金投資をするほど損失が拡大します。
この違いを理解していないと、知らないうちに不利な条件で遊んでいることになります。
また、46枚貸しが当たり前になったことで、設定配分やイベント内容で差別化を図る店舗も増えています。
単純な貸出枚数だけで判断せず、再プレイ条件や貯メダル対応の有無、交換率などを総合的に見て判断することが重要です。
特に、等価交換可能な地域を中心に立ち回ることで、無駄な損失を減らすことができます。
まとめ
46枚貸しという仕組みは、単なる貸出枚数の違いではなく、業界全体の構造変化を象徴している制度です。
消費税率の上昇によって、ホールが税負担を吸収しきれなくなる事態になりました。
その調整策として導入されたのが、46枚貸しです。
結果的に、その差を負担しているのは打ち手です。
制度上は等価に見えても、実際の遊技環境では投資効率の悪化や、機械割の低下といった形で影響を受けています。
しかし、46枚貸しが一概に悪いわけではありません。
等価交換を維持している店舗では、出玉を多く獲得した際の換金効率が上がり、理論上の期待値も高まります。
ハイエナや高設定狙いを中心とした、立ち回りを行う打ち手にとっては、より効率的に収支を伸ばせる環境にもなります。
一方で、現金投資を中心に遊技する打ち手や、長時間打つ層にとっては確実に損を積み重ねやすく、従来より厳しい環境といえます。
最終的に、46枚貸しの時代で求められるのは、仕組みを理解したうえでの戦略的な立ち回りです。
貯メダルの活用や交換率の確認、再プレイ条件の把握といった基本的な対策が、勝率を大きく左右します。
税制や業界のルールが変わらない限り、この仕組みは今後も続く見込みです。
だからこそ、打ち手が制度に適応し、自分の遊技スタイルを最適化していくことが、46枚貸しの時代を生き抜くための、最も現実的な勝ち方だといえるでしょう。
「じゃ、等価交換か非等価(高価・低価)では、一体どれがいいの?」
って疑問に思った人は、こちらの記事で換金率の仕組みを解説しています。
交換率があやふやなままでは、勝つことはできませんよ。


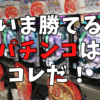
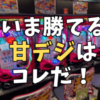
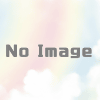


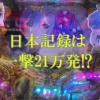









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません